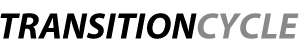よくある現状・現実
パーパス(存在意義)を明確にできない企業の持続的な繁栄は難しいとまで言われるほど、欧米を中心としてパーパスへの注目が集まっています。例えば、下記のようなニーズからパーパスを策定したいと考える企業も多いのではないでしょうか。
- 不確実な事業環境における柔軟でスピーディな意思決定の実現
- 自社の存在意義を明確化することによる従業員エンゲージメントの向上
- 一貫性のある戦略構築や戦略遂行の加速化
- 米国で既に50%を超えるミレニアル世代へのマーケティング訴求力向上
- 「自分はなぜこの仕事をするのか?」を重視するミレニアル世代のリクルーティング強化
- パーパス実現に向けた社外ステークホルダーとの協働・共創の実現
昨今、欧米企業を中心にパーパスの策定が潮流となっており、単にその流れにのるだけではパーパスの策定自体を目的化した取り組みとなりかねません。パーパスはその企業の最も根本的な存在意義であり、What(何)やHow(いかに)ではなく、「なぜその企業が存在しているのか」というWhy(なぜ)への問いの答えとなるものです。そのため、パーパスの策定や浸透においてはミッションやビジョンとは異なる理解をもって取り組みがされることが重要です。
問題の原因・本質
パーパス策定のみならず、真にパーパスドリブンな組織を築くためにはトップのリーダーシップが不可欠です。MITスローン経営大学院で上級講師を務めるピーター・センゲ氏は著書『学習する組織』の中で、「信奉理論」と「使用理論」について言及しています。信奉理論は自分が口にし、信奉する理論です。使用理論は実際に自分が行動上使用している理論です。信奉理論と使用理論は必ずしも一致しません。つまり、トップがパーパスを信奉していると語りながら、実際にそこから外れた使用理論を持っている場合、パーパスへの取り組みは頓挫することになるでしょう。
パーパスに取り組むトップは、様々なジレンマないしチャレンジに直面します。例えば、自社の経済的利益と社会へのポジティブなインパクト、組織内での効率性の追求と社員一人ひとりの幸福度、階層型の組織構造の維持と権限移譲された個人によるフラットな組織への転換などです。組織のトップには、困難な意思決定の状況において自社のパーパスに真摯に向き合いながら選択をしていけるのかが問われることとなります。
知識やスキルとは異なる人間性の発達を扱う「成人発達理論」と近年の組織論によれば、トップの器が組織の器となると言われています。そのため、パーパスドリブンな組織の基盤となるパラダイムとその経営手法を理解することがトップには求められるのです。
ソリューションの特徴・アプローチ
パーパスに関する弊社ソリューションの特徴は、主に3点に集約されます。
1点目は、トップに対するエグゼクティブコーチングを通じて、パーパス策定の前段階において、組織のあるべき姿をゼロベースで描いていくことです。パーパスドリブンな組織構築にはいくつかの必要条件が存在します。またもっと言えば、全ての組織がパーパスドリブンな組織を目指すことが正解ではありません。だからこそ、パーパスやパーパスドリブンな組織についての解像度を高めること、トップが抱えるジレンマや違和感、トップの意志としての理想の姿や個人としての重要な価値観などを明らかにすること、事業の特徴や社員の現状などリアリティを把握することなどがプロジェクトの初期段階で重要となります。結果的に、時には数か月~1年単位で時間をかけて、トップの発達に寄り添いながら、段階をおって組織を進化させていくこともあります。
2点目は、企業パーパスと同様に、個人のパーパスを重視する点です。言い換えれば、企業パーパスができた後にその素晴らしさを社員に理解してもらう・追従してもらうのではなく、企業のパーパスと個人のパーパスが共鳴することにより、パーパスが力を持つことを重視するスタンスをとります。そのために、企業が社員個人のパーパスを探求することを奨励しながら、社内に適切な慣行を築く支援なども実施します。
3点目は、パーパスに基づく社外との協働・共創を推進するアプローチを提供する点です。弊社が考えるパーパスの定義とは、社会性を含みながら、簡単には達成できない大きな意義を有するものであり、社内外にパーパス実現に向かうエネルギーを生み出すものです。しかしながら、マルチステークホルダーでの取り組みは典型的に関係性、共通認識、共有ビジョンの構築が困難であり、通常とは異なるアプローチや手法が求められます。弊社では「U理論」や「学習する組織」、「シナリオプランニング」などをベースに、パーパス実現に向けたマルチステークホルダーでのプロジェクト支援などにも対応します。