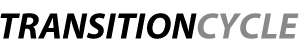よくある現状・現実
大手上場企業からベンチャー企業まで規模を問わず、経営陣の一体感を高めたいというニーズが存在します。その中には、関係性の悪化により具体的な問題が顕在化しているケースから、漠然とした不安感まで幅広い状況があります。具体的なニーズとしては、以下のような事項が考えられます。
- 社長が未来の事業環境に強い危機感を有しており、他の役員とも危機感を共有したい
- 会社が目指すべき方向性や戦略に関して共通認識を構築したい
- 一人ひとりの強みや個性を理解し尊重し合える経営チームを築きたい
- 組織のフェーズが変わりつつある中で経営陣の考えを議論・対話し尽したい
- 経営陣一人ひとりが自らのリーダーシップについて内省し支援し合う場をつくりたい
一般的に、組織の階層の上にいくほど弱みを見せづらく、相談相手も少なくなり、また日々の忙しさやプレッシャーの中で重要だと感じながらも緊急性が低いテーマが後回しにされる傾向があります。その最たるものが経営メンバー間での一体感や共通認識の醸成といったテーマです。忙しい中での時間確保が必要となりますが、経営陣が一枚岩化することで組織や業績に与えるインパクトは大きく、レバレッジが期待できる取り組みでもあると言えます。
問題の原因・本質
経営陣の一体感・共通認識醸成というテーマの難しさの一つが、「良くなる前に悪くなる」という道筋を経ることです。本テーマへの問題意識を感じているほとんどのケースにおいて起こっていることは、本音が話されていないということです。
世界中の社会課題や紛争解決に関わってきたファシリテーターのアダム・カヘン氏は組織での会話の質をいくつかのフェーズに分けて説明します。1つ目の「儀礼的会話」では、話し手は礼儀正しく、相手に合わせて本音は語られず、聞き手も過去のパターンから予測しながら慣習に沿って受け答えをします。2つ目の「討論」では、互いに本心からの意見が述べられますが、両者は対立し、どちらが正しいかの論争に陥りがちです。3つ目の「内省的対話」では、意見を述べる際も自分自身の考え・前提に内省的であり、聞き手も相手の意見の背景にある事柄を探求するように会話がなされます。この3つのフェーズからすれば、多くの組織での経営陣での会話が1つ目の「儀礼的会話」にとどまっているということです。
もちろん業務上必要なことは一定程度「討論」ベースで会話されているという状態も考えられます。一方で、その会話の最中「本当は思っているが言わない」という場面も多いのではないでしょうか。
本音が出ない理由は冒頭に述べた「良くなる前に悪くなる」にあります。つまり、「儀礼的会話」を超えて「討論」に入った時、それまで語られなかった本音がテーブルの上に持ち込まれ、関係性が一時的に悪化するのです。感情的にも不快な感情を伴い、場合によっては修復不可能な関係性に陥る可能性があるなど、人は無意識的にそれらの可能性を感じとって本音を覆い隠します。
また、経営メンバーはテーマにおける当事者となるため、互いの本音を出し合う場を構築するというファシリテーターの役割を果たすことが難しく、外部のファシリテーター/コンサルタントが支援に入ることが求められます。
ソリューションの特徴・アプローチ
弊社ソリューションの特徴は、思考だけではなく、本人さえも気づいていなかった感情やニーズにアプローチするというものです。ビジネスの世界において感情やニーズを語ることは一般的には望ましくないと言われています。「感情的になるのはよくない」「ロジックがない話をするな」といった言葉がそれを示唆しています。
思考やロジックは一つの正解がある中でそれを求める場合には有効です。一方で、誰しもが持つニーズがあり、多義的な真実を語ろうとするときには限界もあります。例えば、「自分は公正な評価・報酬を受け取っていない」という主張をする人が本当に求めていることは「他の経営陣とお互いに分かり合いたい」というニーズだったこともあります。
弊社では、感情とニーズを扱うコミュニケーション技法であり臨床心理学者マーシャル・B・ローゼンバーグ博士によって体系化された「NVC(Nonviolent Communication)」など多様なアプローチをもって本音を出し合い、相互信頼を築き、その先にある共に実現したいものを語り合う支援を提供します。